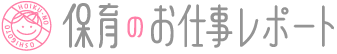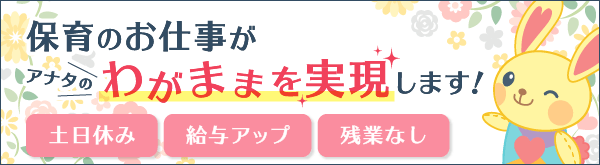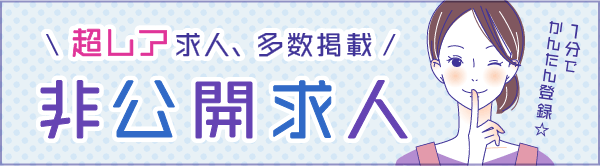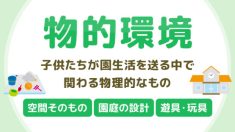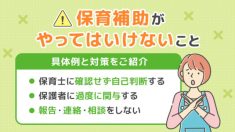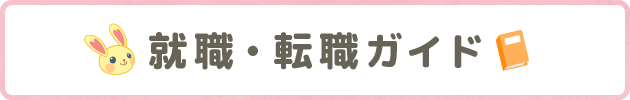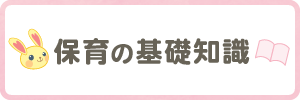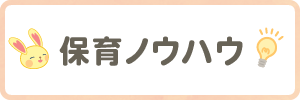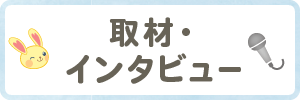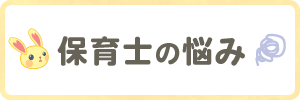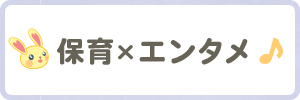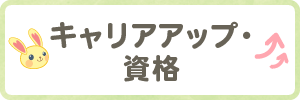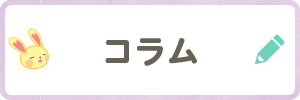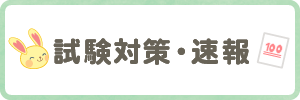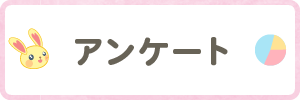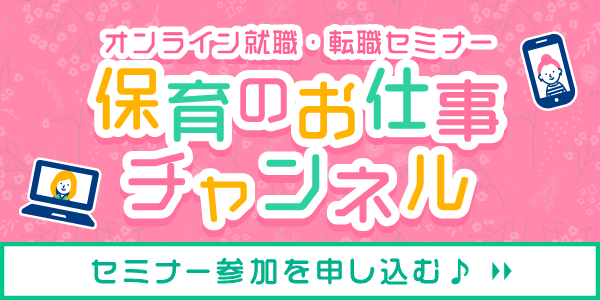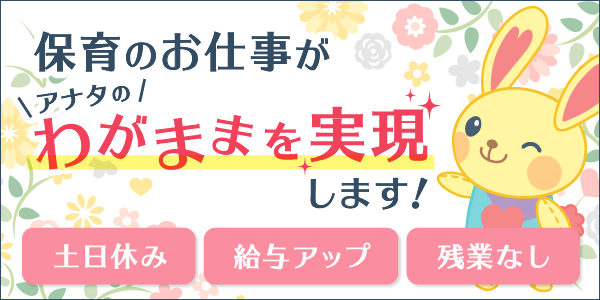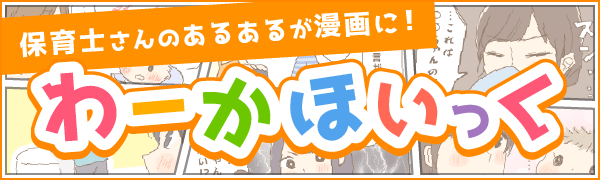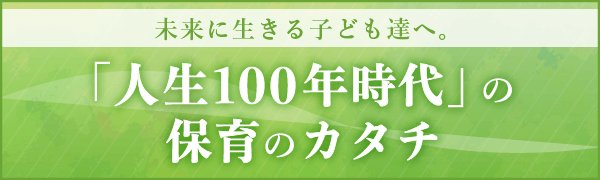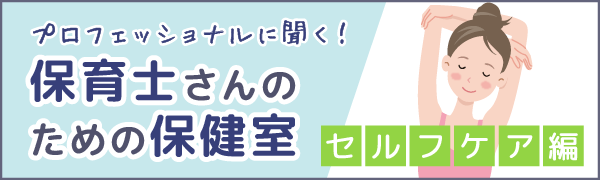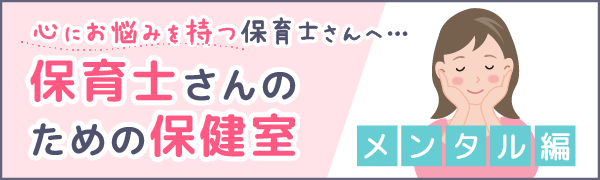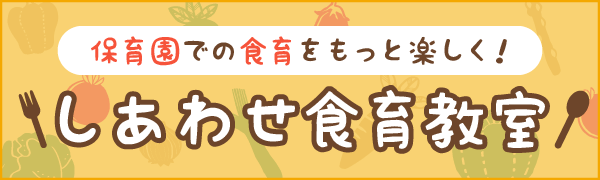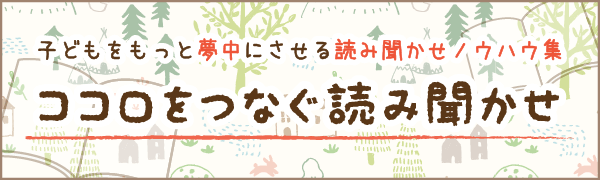日々の保育の中で「もう少し丁寧に関わりたいな」「人手が足りず、子ども全員を十分にサポートできていないかもしれない」と感じることはありませんか。
様子が気になる子どもがいても、人手が足りずサポートが難しい場合があります。そのようなときに保育現場で活用できる仕組みが加配です。加配とは、発達や行動面に特別な配慮が必要な子どもをサポートするために、保育士を追加で配置することです。加配保育士が加わることで、子どもが活動に参加しやすくなり、クラス全体にも落ち着きが生まれることが多くあります。
本記事では、加配の意味から実施状況まで、詳しく紹介していきます。加配制度を活用して、対象児がのびのびと活動できるようにサポートしていきましょう。
【この記事で分かること】
- 加配の定義
- 加配保育士の支援内容
- 加配の実施状況
- 加配に関する支援制度
もくじ
加配の基礎知識
まずは加配について、以下の3つの観点から詳しく解説します。
- 加配の定義
- 加配の対象
- 加配を行う目的
加配の基礎知識を理解すると、対象児への理解がより深まります。それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
加配の定義
加配とは、発達支援や特別な配慮が必要な子どもたちに対して、個別に対応するために保育士を追加で配置することです。
通常、追加配置される保育士のことを加配保育士と呼びます。幼稚園の現場では加配の先生という呼び方が多いですが、施設によって呼び方が違います。
2019年の内閣府の調査では、保育所に通う障害のある子どもの数が約7万8千人となり、過去10年間で増加傾向にあるようです。また障害のある子どもを受け入れる保育園も増えており、2019年には全国で約1万9千か所の保育園が障害児保育を行っています。
このように保育の必要性が多様化する中で、障害のある子どもの保育を支える加配制度がより大切になってきています。これからも、一人ひとりの子どもに合わせた丁寧な保育を行うため、加配保育士の役割は重要といえるでしょう。
※参考:内閣府.「第4章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり」.https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r03hakusho/zenbun/h2_04_01_02.html#z_04_05 ,(参照 2025-06-11).
加配の対象
加配の対象となるのは、以下のような子どもです。
- 障害のある子ども(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など、医学的な診断を受けているケース)
- 発達に特性のある子ども(グレーゾーンを含む。コミュニケーションや社会性の面で特徴的な傾向が見られる場合など)
- 医療ケアが必要な子ども(日常的な医療的ケアや投薬管理、健康管理が必要なケース)
- 外国籍や特別な家庭環境など、個別配慮が必要な子ども(言語面でのサポートや文化的な配慮が必要な場合を含む)
加配の対象判断は医師の診断書や自治体の基準が根拠となることが多く、地域によって具体的な認定基準や手続きが異なる場合があります。
【監修者・礒部はるかのアドバイス】
私がこれまで勤務した保育園では、知的な遅れのある子どもや、発達に特性のある子どもなどを受け入れて、加配保育士を配置していました。ある園ではお腹に人工肛門や人工膀胱をつけた子ども(オストメイト)を受け入れており、オストメイト用のトイレを設置したり、トイレの際に援助を行ったりしていました。そのほか、アレルギーのある子どもへの対応で調理員を加配する園もありました。
加配を行う目的
加配の目的としては、第一に対象となる子どもの安全を確保し、一人ひとりの成長段階に応じた健やかな発達を保障することです。対象児が園での集団生活にスムーズに参加できるよう支援を行い、他の園児たちとの関わりを通じた相互理解を深めることで、クラス全体の安定的な運営を実現できるでしょう。
加配によって保育士の負担を軽減でき、対象児にとってより良い保育環境を提供できるようになります。加配は個別の支援と全体の保育の質の向上の両面において、重要な役割を果たしています。
加配保育士の支援内容

加配保育士は、特別な支援を必要とする子どもたちの成長と発達を支える重要な役割を担っています。主な支援内容は以下の通りです。
- 日常生活のサポート
- 集団行動に参加しやすくするための支援
- 障害に合わせた個別対応
- 保護者へのアドバイス・サポート
それぞれ詳しく解説していきます。
日常生活のサポート
加配保育士の支援内容の一つは、子どもたち一人ひとりの発達段階に応じた基本的な生活習慣(食事・排泄・着脱など)のサポートです。サポートの際は、子どもの発達や特性に合わせて丁寧に関わります。個々の子どもの理解力や運動能力、感覚特性などを十分に考慮しながら、適した支援方法を見つけ出して、サポートすることが求められます。
身辺の自立に向けた意欲を引き出す工夫(声かけ・環境設定)も、サポートの際に重要です。適切なタイミングでの励ましの言葉かけが、自立への意欲を高めていきます。
子どもをサポートする際は、安全確保に気を付けましょう。予測される危険を事前に防ぐとともに、必要な場面での適切な介助を行うことで、安全を確保できます。
集団行動に参加しやすくするための支援
加配保育士は、子どもが集団行動に参加できるよう、活動の見通しを持たせる工夫も行います。活動の流れが分かりやすいように声かけしたり、スケジュールボードで視覚的に伝えたりすると、子どもが安心して活動に取り組めるようになるでしょう。
他の子どもとの関わりの橋渡しも重要な支援です。遊びに誘う際には子どもの興味や性格に配慮し、少しずつ友だちと関わりを持てるようサポートします。トラブルが起きた際には、双方の気持ちを受け止めながら、適切な解決方法を一緒に考えていきましょう。
集団行動に参加しやすくするためには、子ども一人ひとりの特性を理解し、必要に応じて静かに過ごせるスペースを確保したり、少人数での活動を取り入れたりするなど、柔軟な対応が大切です。
【監修者・礒部はるかのアドバイス】
加配が必要な子どもが安心して集団行動に参加できるように促すには、「次は○○するよ」「時計の針が3になったらお片づけだよ」など見通しを持てるような声かけが大切です。必要に応じて、絵カードやタイマーなどの視覚的なグッズを使うと、さらに効果的です。また「○○ちゃん、ブロック好きだよね。△△くんもブロックしてるよ。一緒にどう?」といった形で、子どもの興味を手がかりに、他児との橋渡しをするのもポイントです。
障害に合わせた個別対応
支援する際は、子どもの障害や発達段階における課題を理解し、それぞれの状況に応じた専門的なアプローチと支援方法を適切に選択します。子どもに合った支援をすれば、より効果的な関わりができます。
子どもの得意分野や興味を持っている活動を積極的に取り入れると、子どもの意欲や自信を引き出せるでしょう。障害に合わせた個別対応をすることで、子どもの成長につながっていきます。
保護者へのアドバイス・サポート
保護者に対しては、園での子どもの様子を具体的に伝えましょう。連絡帳や送迎時、面談などの機会を活用して、子どもの成長や活動の詳細を伝えます。
保護者と接する際は、保護者の気持ちに寄り添い、共感的な姿勢で関わることを心掛けましょう。保護者の不安や悩みに耳を傾け、少しずつ信頼関係を築いていくことで、子どもの成長を共に見守る関係が育まれていきます。
関わり方に関するヒントや情報提供を行い、保護者が家庭でも子どもとうまく関われるようサポートしていきましょう。
加配保育士の配置の流れ
障害児の受け入れと加配の要請は、保護者からの希望によって開始されます。支援を必要としている子どもの保護者は、主治医の診断書や発達状況の記録、療育手帳などの必要書類を市区町村の担当窓口に提出して申請することが可能です。
申請が受理されると、市区町村側で内容を精査した上で、該当する保育施設に対して受け入れ要請が来ます。この際、子どもの状況や必要な支援の内容について詳細な情報が共有されます。
受け入れが決定した保育施設は、子どもの特性や必要な支援の程度に応じて、加配保育士の配置や支援環境の整備、必要な設備の導入、補助金の申請などの具体的な準備を進めていきましょう。
加配保育士の配置基準は、自治体によってさまざまです。具体的な支援の内容や実施方法、補助金の額、申請手続きなどは、各自治体の規定や施設の体制によって対応が異なります。詳細については、各自治体の担当窓口に確認しましょう。
加配の実施状況
全国保育協議会の2021年度会員実態調査によると、回答を寄せた全国保育協議会会員施設(回答4,102件)のうち、障害児保育を実施している施設は全体の76.6%に上ることが明らかになりました。
さらに障害児保育を実施している施設に焦点を当てると、84.4%が障害児加配保育士を配置しています。各施設における配置人数を見ると、平均して2.3人の加配保育士が配置されており、加配の支援体制が整えられています。
※参考:全国保育協議会.「会員実態調査報告書2021_表1」.https://www.zenhokyo.gr.jp/cyousa/r04_07/kaiin2021.pdf ,(参照 2025-06-11).
【監修者・礒部はるかのアドバイス】
全国保育協議会の調査では、障害児保育の対象ではないものの特別な支援が必要な子どもが「いる」と回答した施設は、障害児保育を実施する施設の83.8%となっています。これは発達の特性だけでなく、家庭環境の影響による情緒・行動面の不安定さ、外国にルーツをもつ場合など、診断がない場合でも個別の配慮や支援を必要とする子どもが多数存在していることを示しています。そのため、障害の有無に関わらず、多様な支援が必要な子どもたちを支える体制作りの一環として、より柔軟かつ実情に即した加配の措置が求められています。
加配に関する支援制度

保育現場では加配保育士の配置のために、さまざまな制度が設けられています。以下では、保育士向けと施設向けの主な支援制度について説明します。
<加配に関する支援制度>
- 保育士向け:保育士等キャリアアップ研修
- 施設向け:療育支援加算
- 施設向け:障害児保育加算
保育士向け:保育士等キャリアアップ研修
保育士等の専門性の向上や保育現場を支えるリーダー的職員の育成を目的として、キャリアアップ研修が用意されています。特に障害児保育の分野は、加配保育士の専門的なスキルと知識の向上に直結する内容となっており、実践的な学びの機会を得ることが可能です。
研修を修了した保育士は、専門性の向上が評価され、処遇改善の対象となります。
※参考:東京都.「東京都保育士等キャリアアップ研修」.https://hoikushicareerup.metro.tokyo.lg.jp/ ,(参照 2025-06-11).
【監修者・礒部はるかのアドバイス】
キャリアアップ研修では「障害児保育」という分野も学びます。この研修では、知的障害や自閉症スペクトラムなどの障害のある子どもの特性や合理的配慮の具体例を学び、発達段階に応じた個別支援の方法を習得できます。環境調整や集団生活での関わり方、保護者への支援方法も詳しく解説されているため、日々の保育現場や保護者支援でも専門的な視点を取り入れた支援を実現できますよ。
施設向け:療育支援加算
療育支援加算とは、障害のある子どもに対してより専門的かつ個別的な支援を行うために、保育施設が追加で受け取れる補助金制度のことです。地域住民などの子どもの療育支援に取り組む場合、主任保育士が本来の管理業務に専念できるように、補助職員を配置するための経費を負担してもらえます。
経費は国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1の割合で負担する仕組みとなっています。
施設向け:障害児保育加算
障害児保育加算とは、障害のある子どもを受け入れる保育施設に対して、保育士の加配に必要な費用を国や自治体が補助する制度です。障害児2人につき保育士1人を配置するために必要な費用を、国や自治体から援助してもらえます。
経費は療育支援加算と同様、国が2分の1、都道府県、市町村が4分の1の割合で負担してもらえます。
まとめ
加配は「もう少し丁寧に関わりたい」「安心できる環境で保育を受けてほしい」という現場の思いを実現できる制度です。加配保育士が日常生活の見守りや介助、集団行動への橋渡しなどを丁寧に行うことで、対象児が自分のペースで過ごせる環境を整えられます。
「保育のお仕事」では保育士や幼稚園教諭、児童指導員など保育に関わる幅広い職種の求人情報を豊富に取り扱っています。職場探しに役立つさまざまな情報をお届けしているので、保育の職場探しでお悩みの方は、まずはLINEの友だち登録をしてみてください。
監修者情報

礒部はるか
保育士資格・幼稚園教諭一種免許状を保有。大学卒業後、学童・児童館にて保育士として従事。その後、保育園にて乳幼児クラスを担当。現在は複数の保育メディアにてライター・編集者・監修者として活動。
よくある質問
加配とは?
加配とは、特別な配慮や支援が必要な子どものために、保育士を通常の配置基準に加えて配置することです。一人ひとりの子どもに対するきめ細やかな配慮やサポートを実現するためには、通常の基準以上の保育士を配置することが望ましいとされています。
加配により、子どもたちの安全確保はもちろんのこと、個々の発達段階や特性に応じた適切な支援が可能です。保育士の負担軽減にもつながり、保育の質の向上が期待されます。
加配保育士の仕事内容は?
加配保育士は、日常生活でのサポートを行い、子どもたちが集団活動により積極的に参加できるような環境作りと細やかなサポートが仕事です。それぞれの子どもの障害や発達状況に合わせた丁寧な対応を行うとともに、保護者との定期的な面談や相談対応、家庭での育児に関する具体的なアドバイスやサポートなどを実施します。
保育園で加配に関して受けられる支援は?
国による加配制度として、療育支援加算と障害児保育加算の2つの制度があります。療育支援加算は、障害のある子どもに対して専門的な個別支援を行うための補助金制度です。障害児保育加算は、障害のある子どもを受け入れる保育施設に対して、保育士の加配(追加配置)費用を国や自治体が補助する制度です。
これらの加配制度により、障害のある子どもたちへのより手厚い支援と適切な保育環境の提供が可能となります。