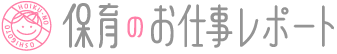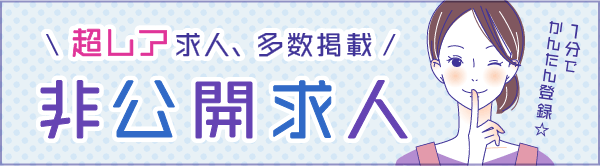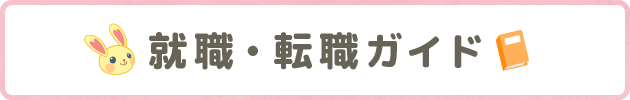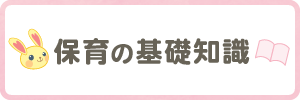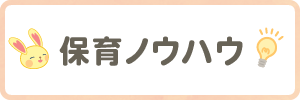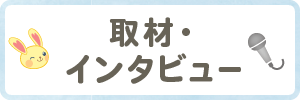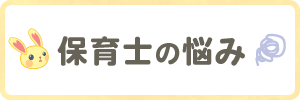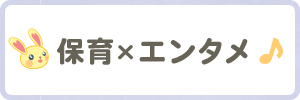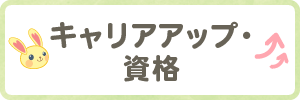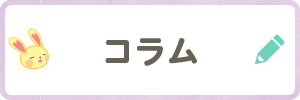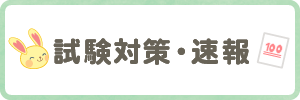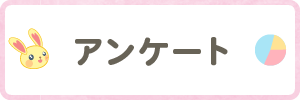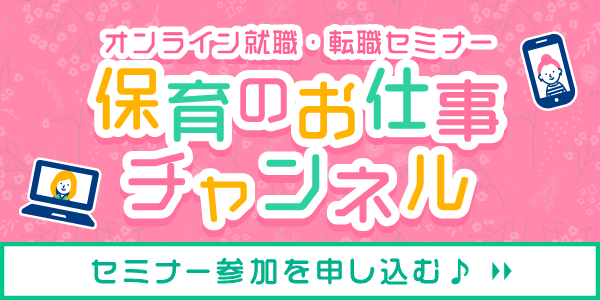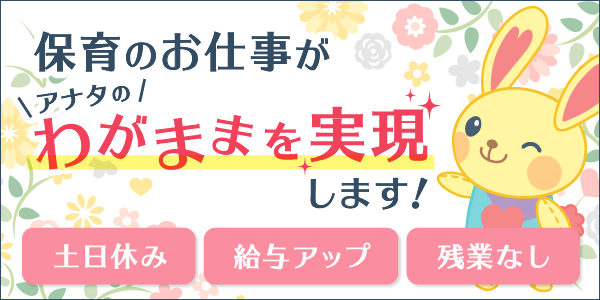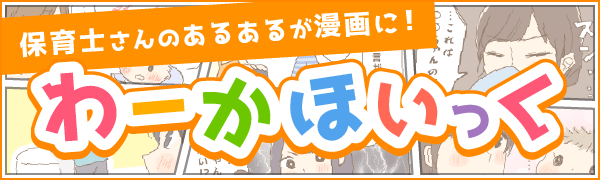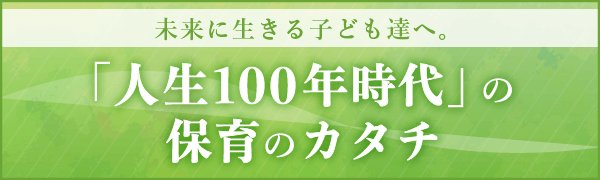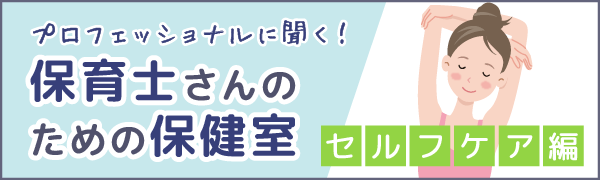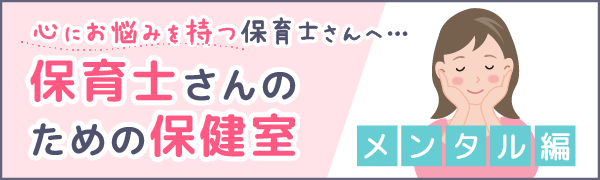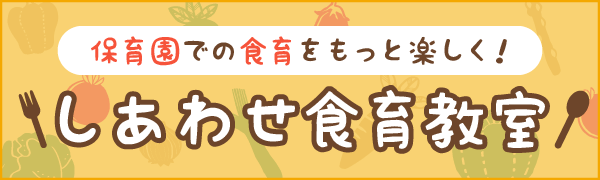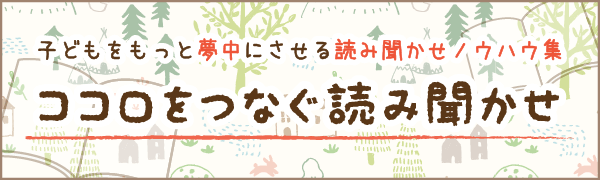深刻化する待機児童問題の対策のために、2006年から設置されるようになった「認定こども園」。
「幼児教育」と「保育」を一体的に行う、幼稚園と保育園を合体させたような施設です。地域の状況や保護者のニーズに応じて選べるよう、さまざまなタイプの認定こども園があります。
平成28年度に内閣府が発表した資料によれば、全国の認定こども園の数は平成23年~平成28年の5年間でおよそ3300園も増加しているそうです。これからますます、認定こども園は増えていくことでしょう。

そこで今回の記事では、埼玉県松伏町に構える幼保連携型認定こども園「こどものもり」を取材してきました!

-
*シリーズ「保育ノゲンバ」は、保育施設や保育士・園長先生などにフォーカスし、保育の現場(ゲンバ)をお伝えするリポート取材連載です。
もくじ
「認定こども園 こどものもり」とは?

認定こども園 こどものもりは、社会福祉法人桜福祉会が運営している幼保一体の認定こども園です。
現在の形になったのは平成27年の4月ですが、前身となった「認可外まつぶし保育園」の開園(昭和46年4月)から数えると、現在に至るまで実に47年もの長い歴史を持つ園となります。
若盛正城園長によれば、
とのこと。実際に、若盛園長もご息女と親子二代で園を支えていらっしゃいます。
こどものもりにはどんな特徴があるの?
こどものもりの大きな特徴として、「家庭的な温もりに包まれた保育環境」「異年齢保育」「コーナー保育システム」といったものが挙げられます。
- 家庭的な温もりに包まれた保育環境
-
温かい家庭の延長として子どもたちに生活してもらうことを第一に考えているこどものもり。たとえば、ランチのときにはゆったりとした音楽をかけて、子どもたちが落ち着いて食事できるようにしています。
また、保育教諭の先生は必要なとき以外にはエプロンをつけません。決まったユニフォームもなく、各々が普段着で子どもと触れ合っています。これもまた、家庭的な温もりを大切にしているため。
園で過ごす子どもの生活の中では、保育教諭も重要な環境のひとつと位置付けられています。そのため、先生ひとりひとり服装が違って当たり前、という考え方です。だからこそ、子どもたちから「先生、今日お洋服可愛いね!」といった声が上がることもあるそう。
子どもの生活を豊かにするのが保育教諭のお仕事ですから、生活の中にいるのに作業着であるジャージなどは違うかなと思っています。
- 異年齢保育
- こどものもりでは、0,1,2歳児は年齢に応じた保育室での生活を中心とし、3,4,5才児は4つのグループに分かれて異年齢での生活を中心としています。年齢の高い子は低い子をいたわり、年齢の低い子は高い子を敬うことなどを通して、共に助け合いや信頼、思いやりの心を育てることを目的としています。
- コーナー保育システム
-
園の中にはさまざまなコーナーが設置されており、子どもたちは自主的にやりたい遊びに取り組むことができます。
先生の指示で動くのではなく、子どもの主体性を大切にした保育を行うことで、子どもの意欲や自己充実感を育てることを目的としています。
| どのようなコーナーがあるの? | |
|---|---|
| 絵のコーナー | 絵を描くことで感性を養い、自分の心持ちをていねいに表現する楽しさを味わう |
| 造形のコーナー | 工作遊びによって、いろいろな素材を自分なりに工夫し、創造性を養う力を身につける |
| 表現のコーナー | 自分の思いを身体で表現し、心の充実と安定感を育てる |
| ごっこのコーナー | 大人の真似から生活の仕組みやあたたかな環境づくりへの体験をを学ぶ |
| 外遊びコーナー | 身体を動かすことで、丈夫な身体作りや遊びのルールなどを学ぶ |
| クッキングコーナー | 園内に実る果物や育てた野菜を料理して食べたり、出来たものを他へ振る舞ったりする体験を通して、季節の恵みに感謝する心を育てる |
| 自然のコーナー | 野菜や花を育てたり、虫を飼育したりして、思いやりや感動の心を育てる |
さっそく!施設の中を見学させてもらいました
 エントランス近くの待合いスペース
エントランス近くの待合いスペース園長先生に案内される形で、施設の中を見学させていただきました!
園内はとても広々としていて、自然光をたっぷり取り込む、木の温もりを生かした明るい空間となっていました。北欧風の綺麗なお家、といった印象で、従来の「保育園」「幼稚園」の教室のイメージはまったくありません。
こうした空間づくりも、「家庭的な温もりに包まれた保育」のためのこだわりです。
 保育室へ向かう廊下。なんだか森の中にいるよう!
保育室へ向かう廊下。なんだか森の中にいるよう! 広々としていて、いわゆる「教室」っぽさはありません。インテリアも素敵
広々としていて、いわゆる「教室」っぽさはありません。インテリアも素敵 子どもたちが園で収穫したプラムをジュースにしています
子どもたちが園で収穫したプラムをジュースにしています 造形のコーナーに置いてあるワゴンには、子どもが必要とする教材がきれいに並んでいます
造形のコーナーに置いてあるワゴンには、子どもが必要とする教材がきれいに並んでいます子どもたちが好きな道具や教材を使えるようになっているとともに、自分で片付けられるよう、戻し方がわかるように色別などや配置の写真をつけています。
 屋内から張り出した形の開放的なテラス
屋内から張り出した形の開放的なテラスこのクッキングコーナーで子どもたちが実際に調理しているそうです。「カフェみたいでしょ」と園長先生もニッコリ。
 テラスの先につながる西側のお部屋がごっこ遊びのコーナー
テラスの先につながる西側のお部屋がごっこ遊びのコーナー子どもたちが好きな衣装を選んで遊べる、ごっこ遊びやパズル遊びのコーナーです。
 園庭というより、木陰や子どもたちが座るベンチのある、家の庭のよう
園庭というより、木陰や子どもたちが座るベンチのある、家の庭のようおやつの時間になりました!
子どもたちのおやつの時間にお邪魔しました。
森のひだまりをイメージした大きなランチルームでは、3~5歳の子どもたちが各々自分でおやつをもらい好きな席に座って、ゆったりとオルゴールの曲を聞きながらおやつを食べています。

0~2歳児は自分達のお部屋でおやつタイム。大きな組からお手伝いに来てくれる子どももいるようです。

働く保育教諭さんに聞いてみた
実際に「認定こども園 こどものもり」で働いている保育教諭の先生にもお話をお伺いしました。
今回インタビューに答えてくださったのは針ヶ谷夏美(はりがやなつみ)先生(24)。初就職から「こどものもり」を選び、保育士資格・幼稚園教諭免許の両資格を取得している針ヶ谷先生に、働く側から見えるこどものもりの魅力をお聞きしました。

――「認定こども園 こどものもり」を選ばれたきっかけは何でしたか?
針ヶ谷先生:こどものもりを知ったきっかけは、大学の授業で担当の教授から、この園で作成されたDVDを見せていただいたことです。当時から私は「保育者中心の一斉保育」というものが自分の保育観には合わないな、と思っていたので、こどものもりでは子ども主体の保育をしていると聞いて興味を持ちました。そのことから就職の一年前に、自分で電話して実習させていただきました。
その中で自分の保育観との一致を感じたり、まわりの先生方の子どもとのかかわり方を見て、温かくていねいな保育の姿に共感できたので、就職先として志望しました。
――保育をする上で、意識していることなどはありますか?
針ヶ谷先生:「子どもの気持ちに寄り添う」「常に笑顔でいること」「子どものやりたい気持ちを読み取ること」などを心がけています。いつも笑顔でいる先生には、子どもたちも安心して気持ちを伝えられると思うので、そこは大切にしています。

――他の保育者さんに、「こどものもり」はおすすめしたいですか?
針ヶ谷先生:そうですね、友たちにもたくさんこどものもりのいいところの話をしています。大学では子ども主体の保育について学んでいるのに、友たちが勤めている園は一斉保育で先生主体のところがほとんどで、そのギャップに悩んでいる仲間も多い印象ですね。なので、こどものもりの話を聞くと、「やっぱりそれが本来の姿だよね」と我に返ったような反応をされることが多いです。自分は恵まれていると思います。
一日の仕事の流れ
針ヶ谷先生にお聞きした、「こどものもり」での一日のお仕事の流れ(普通番)は以下のようになります。
- 7:50 出勤、掃除
- 自分のコーナーの準備
- 8:15 ミーティング
- それぞれの担当やコーナーに分かれて保育
- 全園児それぞれが主体的に混合で生活、遊ぶ
- ビュッフェスタイルランチ(グループごとに食べる時間が異なる)
- 12:10~14:50 パジャマに着替えて布団で午睡
- 1号児は帰りの会
- 降園 一緒にバスに乗って子どもたちをお送りする
- 園に戻ってコーナーの片付け
- 休憩、明日の準備、ランチルームの掃除
- 16:30 一日の振り返りミーティング
- 18:00 退勤
「ひとつのクラスを担任するのではなく、子どもたちが自由に選べるコーナーを担当しているというのが、通常の保育園・幼稚園とは大きく違った特徴だと思います」とのこと。
編集者より
広くて明るくて優しい木造の施設に、子どもたちと笑顔で接する保育教諭の先生方、そしてお行儀がよくて人懐っこい子どもたち。取材にお伺いした編集部のことも、フレンドリーに迎えてくださいました。
家庭的で自由な保育を大切にしているこどものもり。そこで育った子どもたちが、これからどんな素敵な大人に育っていくのか。取材のさなか、そんな希望ばかりが胸に温かく迫ってくるようでした。
取材にご協力いただきました認定こども園 こどものもりのみなさま、誠にありがとうございました!
次回は、こども園への熱い思いをお持ちの若盛園長にお話を聞きます!お楽しみに!!